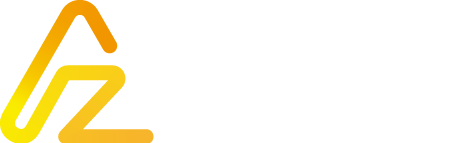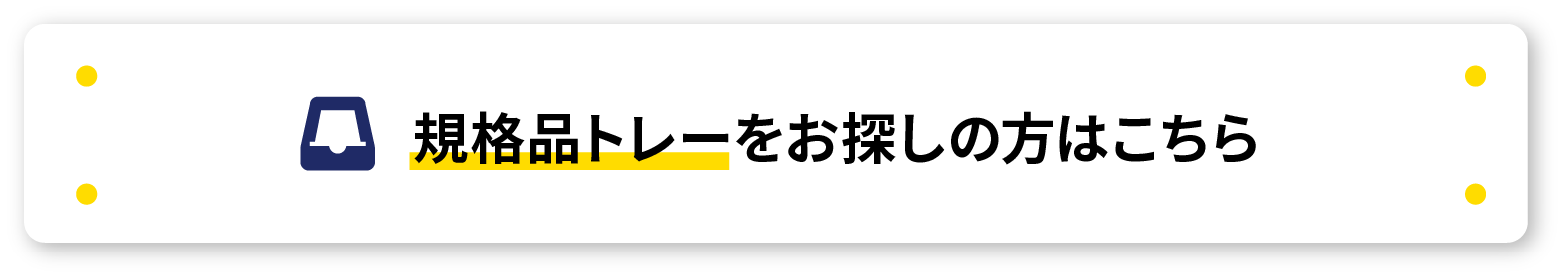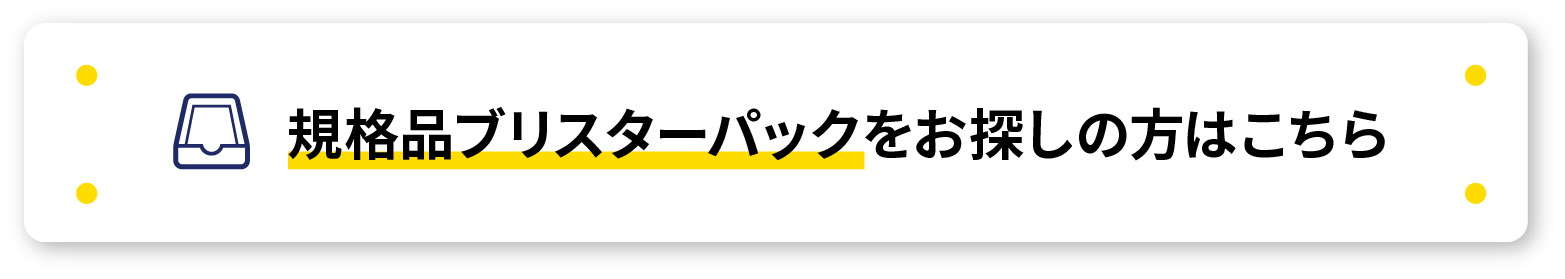100周年スペシャル対談

100周年というこの機会に、吾嬬製作所の歴史を改めて深堀し、確認したい。
その思いから、共に長い時代を歩んできた高宮産業株式会社の取締役本部長 谷野敏之様にお越しいただき、興味深いお話や我々も知らなかったエピソードを伺いました。
> 高宮産業株式会社
古くからお取引が続いている高宮産業様に、吾嬬製作所との歴史的なエピソードを教えていただきました!
吾嬬製作所の歴史と真空成型の始まり
吾嬬製作所/松村社長(以下松村):吾嬬製作所の始まりは、金属の挽物加工やセイコーさん(セイコーウオッチ株式会社)の時計の部品製造からスタートしました。 曾祖父が始めたこの仕事は、そこからさまざまな変遷を経て真空成型に至った。今回100周年を迎えるにあたり、会社の歴史や製品がどう発展してきたのか。我々の知らない経緯やエピソードが知りたくなり、私の祖父の時代から長くお付き合いのある高宮産業様にお声がけさせていただいたんですよ。
高宮産業/谷野本部長(以下谷野):はい。きっかけは昭和46年(1971年)辺りのことだと思います。吾嬬製作所様の先々代社長である松村長治さんがですね、当時装飾業界の理事長をされていました。そして私ども高宮産業は造花業界・装飾業界において四季折々の装飾、たとえばお正月やクリスマスなどで装飾用に用いるプラスチックのシートを販売しておりました。
その関係で、組合の飲み会や会合でたまたま長治さんと知り合ったうちの先代社長が、 吾嬬製作所様が真空成型をやっているということを知り、「我々のプラスチックシートを使って何か一緒にできないだろうか?」と相談したところからスタートしたんです。
その結果、高宮産業は真空成形のおかげで莫大な利益を得ることになりました。それはお葬式やお祝い、パチンコ屋さんの新装開店などで用いられる花輪の開発。当時の花輪は紙製のものが主流だったところに、プラスチックの真空成型の花輪を、長治さんとうちの父の2人で開発したわけです。もうね、爆発的に売れたんですよ!

真空成型の花輪の需要と改良
松村:当時は画期的だった。
谷野:昭和の時代は、お葬式といえば花輪がそれはもう沢山並んでいたものだったんですよ。ただ、昭和40年ぐらいまでの花輪の花は紙製の造花だった。花輪は外に並べるものですから、雨が降ると紙から染料が落ちて汚れるし、すぐダメになってしまうということで、「プラスチックで何かできないだろうか?」と、うちの父である高宮産業の先代社長が、吾嬬製作所の長治さんに投げかけた。そして長治さんが「だったらちょっと試作してみよう」と、色々やってくださった。そこから2年ぐらい経って、最初の矢羽根(花輪の部位)が仕上がったんです。

プラスチックの真空成型による花輪は、このモダン1号という矢羽根からスタートして爆発的にヒットしました。やっぱり紙からプラスチックになったら「持ちが違う!」ということで、日本全国に広がっていくわけです。日本全国の葬儀業界ーーあの頃はお葬式も盛大にやる地域が多かったので、 もうとんでもない勢いで発注が来たんですよ。正直、吾嬬製作所さんも大変だったと思います(笑)。とにかく「早くよこせ、早くよこせ、早くそれをよこせ!」という時期があり、そこから始まって、さらに花輪の改良ユニットというものを作りました。どんなサイズの花輪にも取付しやすいユニットというのを考えた。そこからさらにより花輪が簡単に作れるコンポという製品をどんどん開発していった。と同時に、時代性や地域性などで新しい形のものが望まれるので、これだけの種類の型を毎月起こす勢いでした。もうなんでもありの時代でしたね。

花輪製品の衰退と現在
谷野:しかしこの後、豪華なお葬式というのはどんどん少なくなっていく。ということは花輪はもうほとんど出ない。ということで以降は斜陽産業に入ることになるんですが、でも全くゼロにはならない。非常に嬉しいんだか辛いんだかわからないんですけども(笑)、もう50年以上続いてる業界なもんですから、供給責任ということで現在も作っております。まあ種類はかなり絞って少なくなりましたけれどもね。
松村:コンサートやお祝いで使用する花輪もありますしね。
谷野:ええ、そして一部特許も取っていたということで、花輪はそもそもうちと吾嬬さんがほぼ独占する形でしたから責任をもって続けておりますし、この商品のおかげで高宮産業は未だに続いているということでもあると思っています。そしてこれが吾嬬さんと高宮との歴史ですね。要は、吾嬬製作所の長治さんなくしては、花輪という商品はおそらく出来上がらなかった。うちの父と長治さんという研究熱心なもの同士が、「次はああしよう、こうしよう」ということを積み重ね、いろんなものをお客さんに提供し、日本全国に広まり、これほどまでの種類が出来上がった。そしてここで素晴らしかったのが、この印刷をかけて真空成形をするというのが、 吾嬬さんのかなりの得意分野だったんですよ。色を変えたりとかね。たとえば宝船とか、仏像まである。細かい造形で、しかも凄く大きいんです。それを真空成型で作った。仏像の金型製作には100万近くかかったんじゃないかと思いますね(笑)。
松村:大きいとそれぐらいかかりますからねえ。
谷野:そうなんですよ、そして長治さんはすごかった。これ、図面引くのも大変だったと思うんですよ。お客さんのリクエストでこういうの作っていただいて、対応していただいて、うちは本当に助かっていたんです。
これらの製品はもう作ってはいませんが、今もうちの倉庫に大切に保管しています。
手作りの時代の技術を、どう活かしていくか
松村:しかしこれはすごい。私、このカタログを初めて見ました。
谷野:持ってきてよかった(笑)。
紙からプラスチックに変わって長持ちするのはもちろん、プラスチックだとこれだけ輝く。要はゴールドとシルバーがキラキラしているというのが当時はすごくウケたんです。そして高宮はプラスチックシートの材料をそのまま吾嬬さんにボーンっと入れ、吾嬬さんが真空成型した商品をボーンと積んでお客さんのところに納品するという、それが毎日のように続きました。なので私が高宮に入社した時はもう、完全に肉体労働者です。ひたすらトラックに積んで運ぶ。結構重いんですが、それを10年近く、1990年代半ばぐらいまでやっていましたねえ。徐々に量は減っていったんですけどね(苦笑)。
松村:1990年代だと私はまだ学生ですね、昭和48年生まれなので。高宮さんのお父様、先代社長がうちにいらして、うちの祖父と打ち合わせをしている頃に至っては、まだ小学校にも上がらないぐらいでしたので、確かお父様のお膝に乗せてもらって、頭をなでなでしてもらっていました(笑)。
谷野:はははは。本当にしょっちゅう、長治さんのところに行って打ち合わせをしていましたからね。
松村:はい。毎日のようにというか、毎日いらしてました(笑)。
谷野:そうする中でうちの親父もだんだんとデザイン的なものに興味しんしんとなって行き、もっとこうしたいああしたいという話が出てきて色々衝突もするけれども、仲よくアイデアを話し合っていた。
これ当時、全部フリーハンドで描いて起こしていたんですよね。腕のいい原型師さんが粘土で作って、それを1回真空成形の試作で判断して、そこから金型を作って修正しながらやるという、本当に原始的な、今とはかなり違う作り方でやっていた。本当の手作りの時代でしたね。
松村:今は、その粘土で作れる人もいない。
谷野:そこなんですよ。データがないから当時のデータを作ろうとしても、データを作るだけで費用が数十万かかる。例えば、この仏像だともうデータ化に200万近くかかると思います。だからこの当時のものは、今はもう作るのは難しいんです。
でも、たまに来るんですよ。「高宮さん、昔カタログに載せてたじゃないですか。作れませんか?」と。できるんですけど、でも莫大な費用がかかるので、それは現実的じゃないんですよとお断りしているのが現状です。
松村:3Dスキャナとか、いろんな技術や工具が発達しましたが、そもそもそういうものが全く無い時代に作ったものを再現するのは本当に難しい。むしろだったら、このイメージで別のものを1から作ったほうがまだ現実性がある。
谷野:美大の芸術学科の造形科の卵を引っ張ってきて、「ちょっとこれ作れない?」とやってみてもらっても、作れない。
松村:大学でも専門学校でも学生さんがやるのはCADなんです。多くの学生さんはパソコンの画面上で描き上げて、そこから3Dプリンターで立体化させるという流れなんだと思うんですが、画面上で立体化できても、実際には真空成型にできないんですよ。真空成型の知識がないと、真空成型の型は作れない。
学生さんたちは普通に造形物を作るという発想で作ってるわけですから、例えば食い込んだような形とかも作るけど、それだと真空成型はできないんだよ、ということがわからない。
谷野:ああ。まず、形よりなにより真空成形を知らないと、真空成型の型は作れない。うん、そこは盲点でした。
90年代以降の高宮産業様との挑戦
谷野:90年代に入ると、今度は松村社長のお父さん、征治さん(現会長)の時代になります。ここではゲームセンターが隆盛しました。そしてその頃に、カイダック(塩化ビニル樹脂プレート)という、叩いても割れないプラスチックの素材が登場した。で、 そういう素材を使ってゲームセンターやアミューズメントパーク関連の仕事を吾嬬さんと高宮で一緒にしました。その中で私が携わったのが、池袋のナンジャタウン(1996年開園)で。あのね、ソフビの猫を持って園内を巡るという時代があったんですよ。その猫を置く台座をソフビの会社さんから発注していただいて、ゲームセンター関係にも、真空成形の手助けをしてもらった。猫の台座の型を、征治さんに手彫りで作っていただいたんです。そこから本型を起こしたんですが、征治さんもやはり凄かった!凄く助かりました。そこから、ゲームセンター関連でも真空成型で色々お世話になりました。
これからの吾嬬製作所に望むこと
谷野:今、吾嬬さんでは何か挑戦されていることなどありますか?
松村:はい。ちょっと新しく試していることがあります。うちのスタッフが取り組んでいるんですが、これです。
谷野:え。なんですかこれ、嘘、××××××××ができるの?遂にできたの?凄い!!
松村:まだまだテストの段階ですよ(笑)。
谷野:か、型。これどうやって型作ったんですか、掘った?
松村:いえ、段ボールです。これです。
谷野:ああー、本来まだ見せちゃいけないやつですねコレ。公開できないやつ。何か次が見えてくるじゃないですか。 今日来て本当によかった!
松村:まあ試作なのでこれですけど、失敗しても段ボールだったらまたやり直せるし、その失敗をしないと次が見えてこないので。
谷野:いや、そもそも段ボールでできるってすごいですよ。期待します。将来の展望のところに高宮が多大なる期待を抱いて帰ったと。長治さんの魂は綿々と引き継がれていると確信したと書いておいてくださいよ!(笑)
松村:はははは。うちはこういう、新たなものも含めてさまざまなものが作れる環境にある会社で。高宮さんのところは、販売もするけど、素材にも強い。材料メーカーの代理店もやってらっしゃるから、知見もある。
なので、やっぱりそこでうまくこうマッチしたんだと思っています。本当にありがとうございます。
谷野:とにかく吾嬬製作所さんの良いところは先ほど語ったように、物事の、その商品ができることに関して本当に親身になって、最後まで責任を持っていただけるところです。 お客さんからクレームが来ても即対応していただけるし、その辺はもうお互いの信頼関係でやり取りができるっていうのが非常にやりやすい。なんというか、一緒に組んで話ができるのが楽しい企業さんであることは間違いないです。その上、新しいことにも取り組んでいる。素晴らしいです。こちらこそありがとうございます、これからもよろしくお願いします。